いちじく ~2つの共生②
地中海沿岸のトルコやギリシャなどの国から輸入される乾イチジクやイチジクジャムは、昔は今のものより少し種があり、プチプチとした食感がたまりませんでした。
これらの国では花粉を運ぶイチジクコバチが元気で、メスとオスの木があります。
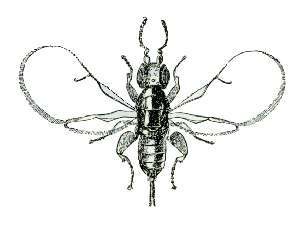
花が見えないのにどうやって受粉させるのでしょうか。
イチジクのメスもオスも果嚢の頂点に小さな穴があります。ここから大変小さな蜂(イチジクコバチ)が出入りして受粉して、また中に産卵しているわけです。
イチジクはイチジクコバチに子どもの家と食料を与える替わりに自分の子孫(種)を残してもらいます。
これがもう一つの共生です。
驚くことにイチジク属のそれぞれの種類毎にそれに対応したイチジクコバチの種類があるということです。
最近の研究ではイチジク属のそれぞれのDNAをたどれば一つの種類に収束し、またイチジクコバチのDNAをたどれば一つの種類にたどり着くことがわかりました。
およそ9000万年前の一つ種類のイチジクとイチジクコバチから今のイチジクとイチジクコバチが750種類ほど生れたということです。
つまり、イチジクとイチジクコバチは互いに助け合って、進化してきたわけです。
これを共進化といいます。
京都でみられるイチジクの仲間には落葉性のイヌビワがあります。また、つる性での常緑のヒメイタビが垣根に使われることがあります。

イヌビワはそれほど美味しくありませんが、イタビの仲間のオオイタビは大変美味です。
私は、小学校の時に福岡県の古賀というところに住んでいて、日曜日はいつも自転車で遠くの同級生の遊び場に行くのを常としていました。
昼はれんこん畑で、ザルガニ採りに夢中になって、いつものように川でズボンを洗って乾かし、帰るときになって、Mくんが
「しっとうや、イタビ」
「なんね、たべれると?」
ということで、友達の秘密の場所に行きました。
鹿部という所にお宮さんがあって、そこの大木に太い蔓がからまっていました。
友達のMくんが蔓を伝ってスルスルと登って、また蔓に足をひっかけて、赤黒い実を採って投げてくれました。
丸い5cmぐらいの実は割ると赤茶のゼリーの粒がびっしりです。
「うまかー、こげなうまかと はじめてたい」 と言うと
「落ちた実はすぐにネズミに食べられるけん、木登りが うもおないと食べられんったい」 と得意な様子。
いまでもMくんの木登りとオオイタビの透明な甘さが忘れられません。
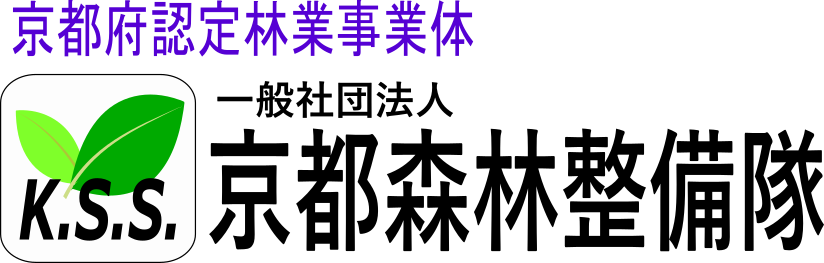


日本の”イヌビワコバチ”と、地中海沿岸の”イチジクコバチ”は、DNAの観点から見てどちらがより起源に近いのでしょうか?
コバチが元々一つの種だったのならばもしかしたら、DNA鑑定の結果次第では日本のイヌビワコバチや熱帯地方のコバチが、果実に入ったままシルクロード、若しくは環太平洋を渡って行ったのかなぁ…なんて、考えてしまいますね♪
コメントありがとうございます。お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
DNAの観点でどちらがより起源に近いか・・・少し調べてみましたがわかりませんでした。
コバチが果実に入ったままシルクロードや環太平洋を渡って行く・・・あり得ない話ではないように思い想像すると楽しくなりますね。